湯川駅 [千葉からZ900RSと1000km超]
徐福公園 [千葉からZ900RSと1000km超]
2022年11月上旬、和歌山に行った際に立ち寄った所。


駐車場へ。
係の人から「1時間以内ならタダだよ」
と言うことで無料っ!

チャイナな建物。すごい立派。

ちなみにこっちは7年前、青森で行った
徐福の里。比べると立派さが・・・・

お約束な顔出しパネル~。

徐福墓畔とその界隈:
中国・秦の時代始皇帝の命で渡来したとされる徐福は
熊野の地に、捕鯨を始めたなど、多くの起源伝承を残
している。実在したとされる徐福の渡来伝承は、全国
に点在するが、何せ紀元前の話。江戸時代紀州初代藩
主徳川頼宜頼宣の命で建てられた徐福の墓は、墓として存
在するのは全国でここだけ。徐福墓畔も栄枯盛衰を重
ねるが、新宮鉄道が開設され、新宮駅ができると、こ
の界隈も大正中期から次第に新開地となってゆく。
佐藤春夫の父がこの界隈に家を建て、春夫の姪がここ
から新宮高等女学校に通い始め、春夫もここで過ごし
たり、執筆したりすることも増えてくる。春夫に「若
草の妻とこもるや徐福町」の句があり、春夫の中学時
代以来の友人奥栄一など文学仲間のたまり場にもなる。

徐福像。

徐福像は青森の方が立派。

そして、徐福の墓。
新宮市指定文化財 徐福の墓:
紀ノ川流域で算出する緑色片岩の自然石に「秦徐福之墓」
と刻まれている。この墓碑は、初代紀州藩主徳川頼宜頼宣が
建立を企て、儒臣李梅渓に書かせたもの、との伝えがあ
る。「熊野年譜」には「天文元年(1736)楠藪へ秦徐福の
石塔立」とあり、約100年後に建立が実現した。
かたわらの「徐福顕彰碑」は天保5年(1834)藩の儒臣仁井
田好古の撰書により建立されるものであったが、和歌山
より運搬の途中海難にあい実現しなかった。現在の碑は
残されていた書によって昭和15年(1940)に建てられたも
のである。

これが徐福の墓。
この下に徐福さんが・・・・

こっちは徐福の碑。
全部、漢字表記っ!

徐福さんに挨拶も終わったので
一時間いないに退出っ。

紀元前、大陸から日本まで船で無事到着
できたぐらいの旅運を貰えたかも。
と思いつつ見学完了。
駐車場へ。
係の人から「1時間以内ならタダだよ」
と言うことで無料っ!
チャイナな建物。すごい立派。
ちなみにこっちは7年前、青森で行った
徐福の里。比べると立派さが・・・・
お約束な顔出しパネル~。
徐福墓畔とその界隈:
中国・秦の時代始皇帝の命で渡来したとされる徐福は
熊野の地に、捕鯨を始めたなど、多くの起源伝承を残
している。実在したとされる徐福の渡来伝承は、全国
に点在するが、何せ紀元前の話。江戸時代紀州初代藩
主徳川
在するのは全国でここだけ。徐福墓畔も栄枯盛衰を重
ねるが、新宮鉄道が開設され、新宮駅ができると、こ
の界隈も大正中期から次第に新開地となってゆく。
佐藤春夫の父がこの界隈に家を建て、春夫の姪がここ
から新宮高等女学校に通い始め、春夫もここで過ごし
たり、執筆したりすることも増えてくる。春夫に「若
草の妻とこもるや徐福町」の句があり、春夫の中学時
代以来の友人奥栄一など文学仲間のたまり場にもなる。
徐福像。
徐福像は青森の方が立派。
そして、徐福の墓。
新宮市指定文化財 徐福の墓:
紀ノ川流域で算出する緑色片岩の自然石に「秦徐福之墓」
と刻まれている。この墓碑は、初代紀州藩主徳川
建立を企て、儒臣李梅渓に書かせたもの、との伝えがあ
る。「熊野年譜」には「天文元年(1736)楠藪へ秦徐福の
石塔立」とあり、約100年後に建立が実現した。
かたわらの「徐福顕彰碑」は天保5年(1834)藩の儒臣仁井
田好古の撰書により建立されるものであったが、和歌山
より運搬の途中海難にあい実現しなかった。現在の碑は
残されていた書によって昭和15年(1940)に建てられたも
のである。
これが徐福の墓。
この下に徐福さんが・・・・
こっちは徐福の碑。
全部、漢字表記っ!
徐福さんに挨拶も終わったので
一時間いないに退出っ。
紀元前、大陸から日本まで船で無事到着
できたぐらいの旅運を貰えたかも。
と思いつつ見学完了。
補陀洛山寺 [千葉からZ900RSと1000km超]
2022年11月上旬、和歌山に行った際に立ち寄った所。


駐車場へ。
ここは裏口っぽいので参道の方へ。


浜ノ宮の大楠。樹齢800年。

浜ノ宮王子社跡:
藤原宗忠の日記、『中右記』天仁二年(一一〇九)十月二十七日
条に、「浜宮王子」とみえ、白砂の補陀落浜からこの王子に
参拝した宗忠は、南の海に向かう地形がたいへんすばらしいと
記しています。『平家物語』には、平維盛がここから入水した
と記されていますように、補陀落浄土(観音の浄土)に渡海する
場所でした。那智参詣曼荼羅には、浜の宮王子の景観とともに
この補陀落渡海の様子が描かれています。また、浜の宮王子で
は、岩代王子(みなべ町)と同様に、「連書」の風習がありまし
た。連書とは、熊野御幸に随行した人々が、官位・姓名と参詣
の回数を板に書いて社殿に打ち付けることです。応永三十四年
(一四二七)の足方義満の側室・北野殿の参詣では、十月一日に
「はまの宮」に奉幣し、神楽を奉納したのち、帯や本結(紐)を
投げると、神子女(巫女)たちが、争って拾った様子を、先達を
つとめた僧実意が記しています。
三所権現あるいは渚宮と呼ばれていましたが、現在は熊野三所
大神社と称しています。なお、隣の補陀洛山寺は千手堂あるい
は補陀洛寺と呼ばれ、本来はこの王子社と一体のものでした。

こちらが本殿。

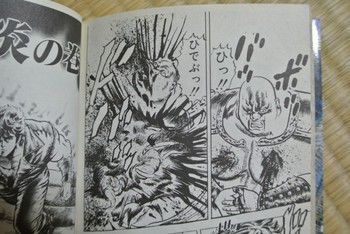
ハート。![[揺れるハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/137.gif)

隣の補陀洛山寺へ。

補陀洛山寺:
補陀洛山寺は、白砂の浜の向こうに広がる太平洋に面して
建てられた天台宗の寺院です。この寺は、南海の彼方にあ
ると信じられていた観音浄土を生きながらにして目指す
「補陀落渡海(ふだらくとかい)」の出発点だったことでも
知られています。

こちらがご本尊。御祈祷を
「追突されませんように!」

そして、このお寺と言えば補陀落渡海の船。

補陀落山渡海とは:
生きながらに南海の観音浄土(補陀洛浄土)を
めざして行われた一種の捨身行である。
平安時代から江戸時代まで20数回にわたり、
那智の海岸から当寺の住僧達が渡海した。
この渡海船は那智参詣曼荼羅を「もとに平成5年
熊野新聞社社主、寺本静生氏によって復元された
もので、入母屋作りの帆船で四方に発心門、修行
門、菩提門、涅槃門の殯の鳥居がある。

捨身行と言うぐらいだったので帰還者は・・・・
スワンボートで外海に出るぐらい無謀だったと。

もしかしたら、補陀落山渡海に参加した僧の
子孫がグアムやサモアにいるのかも。
と思いつつ見学完了。
駐車場へ。
ここは裏口っぽいので参道の方へ。
浜ノ宮の大楠。樹齢800年。
浜ノ宮王子社跡:
藤原宗忠の日記、『中右記』天仁二年(一一〇九)十月二十七日
条に、「浜宮王子」とみえ、白砂の補陀落浜からこの王子に
参拝した宗忠は、南の海に向かう地形がたいへんすばらしいと
記しています。『平家物語』には、平維盛がここから入水した
と記されていますように、補陀落浄土(観音の浄土)に渡海する
場所でした。那智参詣曼荼羅には、浜の宮王子の景観とともに
この補陀落渡海の様子が描かれています。また、浜の宮王子で
は、岩代王子(みなべ町)と同様に、「連書」の風習がありまし
た。連書とは、熊野御幸に随行した人々が、官位・姓名と参詣
の回数を板に書いて社殿に打ち付けることです。応永三十四年
(一四二七)の足方義満の側室・北野殿の参詣では、十月一日に
「はまの宮」に奉幣し、神楽を奉納したのち、帯や本結(紐)を
投げると、神子女(巫女)たちが、争って拾った様子を、先達を
つとめた僧実意が記しています。
三所権現あるいは渚宮と呼ばれていましたが、現在は熊野三所
大神社と称しています。なお、隣の補陀洛山寺は千手堂あるい
は補陀洛寺と呼ばれ、本来はこの王子社と一体のものでした。
こちらが本殿。
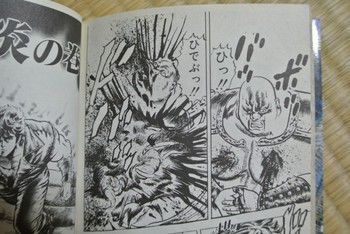
ハート。
隣の補陀洛山寺へ。
補陀洛山寺:
補陀洛山寺は、白砂の浜の向こうに広がる太平洋に面して
建てられた天台宗の寺院です。この寺は、南海の彼方にあ
ると信じられていた観音浄土を生きながらにして目指す
「補陀落渡海(ふだらくとかい)」の出発点だったことでも
知られています。
こちらがご本尊。御祈祷を
「追突されませんように!」
そして、このお寺と言えば補陀落渡海の船。
補陀落山渡海とは:
生きながらに南海の観音浄土(補陀洛浄土)を
めざして行われた一種の捨身行である。
平安時代から江戸時代まで20数回にわたり、
那智の海岸から当寺の住僧達が渡海した。
この渡海船は那智参詣曼荼羅を「もとに平成5年
熊野新聞社社主、寺本静生氏によって復元された
もので、入母屋作りの帆船で四方に発心門、修行
門、菩提門、涅槃門の殯の鳥居がある。
捨身行と言うぐらいだったので帰還者は・・・・
スワンボートで外海に出るぐらい無謀だったと。
もしかしたら、補陀落山渡海に参加した僧の
子孫がグアムやサモアにいるのかも。
と思いつつ見学完了。
蜂の巣壁 [千葉からZ900RSと1000km超]
清納の滝 [千葉からZ900RSと1000km超]
梶取崎 [千葉からZ900RSと1000km超]
11月上旬、和歌山に行った際に立ち寄った場所。
落合博満野球記念館の近く。


駐車場へ。

早速、歩いて梶取崎の方へ。

ん!?これは?

くじら供養碑。

わが町の先人あちは古くから捕鯨業を営み更にこれを継承して
今日に至っている。為に町は栄わが国捕鯨発祥の地として観光
的にも広くその名を博している。
鯨はまた国民生活をも支え国家の発展にも貢献している。その
恩恵は誠に大きい。ここにくじらの供養碑を建立して鯨魂の永
く鎮りますことを祈るものである。建設にあたり町出身の捕鯨
関係者有志のご協力に深く感謝し鯨と共に生きる太地町の発展
を切に祈念するものである。

鯨は生の方が良いな・・・・

供養碑の台座は船。しゃれてる~。
更に進むと

夫婦いぶき(イブキビャクシン):
木の幹周りが、一本は3.3メートル、もう一本も3.2メートル
である。とても古い木なので、江戸自体に海を見張っていた
遠見番所の人が植えたものかもしれない。今も熊野灘の強い
潮風に負けず生き続けるこの夫婦いぶきは、梶取崎の象徴と
して大切にされている。

チッ!。カップルか。

ベンチも2つありやがる・・・・・

続いて梶取埼灯台。

梶取埼(かんとりさき)灯台:
梶取埼は、昔、沖の船がこの岬が見えると梶を取って転針した
ことから名付けられたといわれています。
この岬の北端に小さく突き出た灯明崎には、寛永13年にあんど
ん式の灯明台が紀州藩によって設置され、我国捕鯨産業の発祥
の地大地村を基地とする捕鯨船に取って欠かせない存在であっ
たといわれています。
熊野灘の豪快な男性的な海岸美を一望するこの梶取埼に、沿岸
標識としての重責を担って近代的洋式灯台が建設あれたのは明
治32年11月でした。

今でも現役っ。

灯台からさらに先に進んで・・・・

木をくぐると

梶取崎の最先端に到着っ!

男性的な海岸美を見て、駐車場へ。

男性的な熊野灘には漢一人が良く似合うっ!
と思いつつ見学完了。
落合博満野球記念館の近く。


駐車場へ。

早速、歩いて梶取崎の方へ。

ん!?これは?

くじら供養碑。

わが町の先人あちは古くから捕鯨業を営み更にこれを継承して
今日に至っている。為に町は栄わが国捕鯨発祥の地として観光
的にも広くその名を博している。
鯨はまた国民生活をも支え国家の発展にも貢献している。その
恩恵は誠に大きい。ここにくじらの供養碑を建立して鯨魂の永
く鎮りますことを祈るものである。建設にあたり町出身の捕鯨
関係者有志のご協力に深く感謝し鯨と共に生きる太地町の発展
を切に祈念するものである。

鯨は生の方が良いな・・・・

供養碑の台座は船。しゃれてる~。
更に進むと

夫婦いぶき(イブキビャクシン):
木の幹周りが、一本は3.3メートル、もう一本も3.2メートル
である。とても古い木なので、江戸自体に海を見張っていた
遠見番所の人が植えたものかもしれない。今も熊野灘の強い
潮風に負けず生き続けるこの夫婦いぶきは、梶取崎の象徴と
して大切にされている。

チッ!。カップルか。

ベンチも2つありやがる・・・・・

続いて梶取埼灯台。

梶取埼(かんとりさき)灯台:
梶取埼は、昔、沖の船がこの岬が見えると梶を取って転針した
ことから名付けられたといわれています。
この岬の北端に小さく突き出た灯明崎には、寛永13年にあんど
ん式の灯明台が紀州藩によって設置され、我国捕鯨産業の発祥
の地大地村を基地とする捕鯨船に取って欠かせない存在であっ
たといわれています。
熊野灘の豪快な男性的な海岸美を一望するこの梶取埼に、沿岸
標識としての重責を担って近代的洋式灯台が建設あれたのは明
治32年11月でした。

今でも現役っ。

灯台からさらに先に進んで・・・・

木をくぐると

梶取崎の最先端に到着っ!

男性的な海岸美を見て、駐車場へ。

男性的な熊野灘には漢一人が良く似合うっ!
と思いつつ見学完了。
南帝陵 [千葉からZ900RSと1000km超]
10月上旬、奈良に行った際に立ち寄った場所。


駐車場へ。

南帝陵:
「ここ国王神社の境内にある」長慶天皇は、文中2年(1373年)
8月御位いを弟の御亀山天皇に譲られ、同年10月まで、紀伊国
玉川の宮におられたが、賊徒の襲来を受け大和の天の川村、
五色谷行在所へお移りになったところが、ここでも賊徒に襲わ
れたので、もはや運命もこれまでと同所の「廻り岩」でご自害
なされた。このとき、近侍のものが、ご遺体を水葬に付したと
ころ、数日を経て御首が、下流の十津川村上野地字河津の渕
(現在地付近)へ流れつき毎夜水底より、不思議な一条の光を発
した。これをみつけた村人が、丁重にこのところへ葬り玉石を
安置してお首塚と呼んだ。以上が南帝陵の十津川村における伝
説の概略である。しかし、歴史上、天皇は弘和2年(1382年)まで
在位されていたことになっており大和誌によると、神社が長慶
天皇の勅願宮となっていることなどから日時が神社創建のとき
と混同されて伝えられたと思われる。いずれにしろ村民が
600年来長慶天皇の在位を確信し、これを奉祀してきたことに
十津川村の特殊性がある。

南朝の天皇なので、こんな御陵を
イメージしたり・・・・・

早速、南帝陵へ。

はぁ、はぁ、はぁ、はぁ・・・・・

国王神社裏手。

表門へ。

国王神社本殿。

国王神社 祭神 長慶天皇。

長慶天皇へ御祈願
「追突されませんように!」

そして南帝陵への階段。

うっ、すごい階段。
ここまでバイクで600km以上走行。

こんなイメージで階段を登ることに。

と、到着っ!

この下には長慶天皇の首が。
まさに玉石っ!


長慶天皇が南斗鳳凰拳の使い手だったら
賊徒から逃走する必要が無かったのに・・・
と思いつつ見学完了。


駐車場へ。

南帝陵:
「ここ国王神社の境内にある」長慶天皇は、文中2年(1373年)
8月御位いを弟の御亀山天皇に譲られ、同年10月まで、紀伊国
玉川の宮におられたが、賊徒の襲来を受け大和の天の川村、
五色谷行在所へお移りになったところが、ここでも賊徒に襲わ
れたので、もはや運命もこれまでと同所の「廻り岩」でご自害
なされた。このとき、近侍のものが、ご遺体を水葬に付したと
ころ、数日を経て御首が、下流の十津川村上野地字河津の渕
(現在地付近)へ流れつき毎夜水底より、不思議な一条の光を発
した。これをみつけた村人が、丁重にこのところへ葬り玉石を
安置してお首塚と呼んだ。以上が南帝陵の十津川村における伝
説の概略である。しかし、歴史上、天皇は弘和2年(1382年)まで
在位されていたことになっており大和誌によると、神社が長慶
天皇の勅願宮となっていることなどから日時が神社創建のとき
と混同されて伝えられたと思われる。いずれにしろ村民が
600年来長慶天皇の在位を確信し、これを奉祀してきたことに
十津川村の特殊性がある。

南朝の天皇なので、こんな御陵を
イメージしたり・・・・・

早速、南帝陵へ。

はぁ、はぁ、はぁ、はぁ・・・・・

国王神社裏手。

表門へ。

国王神社本殿。

国王神社 祭神 長慶天皇。

長慶天皇へ御祈願
「追突されませんように!」

そして南帝陵への階段。

うっ、すごい階段。
ここまでバイクで600km以上走行。

こんなイメージで階段を登ることに。

と、到着っ!

この下には長慶天皇の首が。
まさに玉石っ!


長慶天皇が南斗鳳凰拳の使い手だったら
賊徒から逃走する必要が無かったのに・・・
と思いつつ見学完了。
垂水の滝 [千葉からZ900RSと1000km超]
9月中旬、石川に行った際に立ち寄った場所。

珠洲市 真浦海岸。

駐車場に到着。

垂水の滝:
幻想的な光景が広がる、海に注ぐ滝。
垂水の滝は、山から流れ落ちた水が直接海に注ぐ
という、全国でも珍しい滝です。
冬場には、この海岸周辺で、荒れた海の波が砕けて
水泡となり雪のように舞う「波の花」をみることが
できます。また、風の強い日には、海から季節風に
よって垂水の滝の水が霧状になって吹き上げられ、
水が落ちてこないという現象がみられます。
このことから「逆さ滝」との呼ばれています。

垂水の滝。
尚、隣のトンネルは

通行不可っ!

山から流れ出て来た水は

滝つぼを経て

海へ。

冬場、ここで滝行をしたらあらゆる
試験に落ちないかも。
と思いつつ見学完了。

珠洲市 真浦海岸。

駐車場に到着。

垂水の滝:
幻想的な光景が広がる、海に注ぐ滝。
垂水の滝は、山から流れ落ちた水が直接海に注ぐ
という、全国でも珍しい滝です。
冬場には、この海岸周辺で、荒れた海の波が砕けて
水泡となり雪のように舞う「波の花」をみることが
できます。また、風の強い日には、海から季節風に
よって垂水の滝の水が霧状になって吹き上げられ、
水が落ちてこないという現象がみられます。
このことから「逆さ滝」との呼ばれています。

垂水の滝。
尚、隣のトンネルは

通行不可っ!

山から流れ出て来た水は

滝つぼを経て

海へ。

冬場、ここで滝行をしたらあらゆる
試験に落ちないかも。
と思いつつ見学完了。
ぶつぶつ川 [千葉からZ900RSと1000km超]
11月上旬、和歌山に行った際に立ち寄った場所。


近くの線路脇に駐車。
ちょっと歩く・・・

ぶつぶつ川入口到着。

二級河川 ぶつぶつ川:
ぶつぶつ川は、川の長さわずか13.5メートルの
日本一短い川です。
フツフツと清水が湧き出ていることから、昔から
そう呼ばれてきたそうです。今でも野菜や道具、
洗濯物を洗ったりと、生活に欠かせない貴重な水
源です。周辺の環境は、地元の方々の努力で維持
され、豊かな生物多様性が守られています。この
環境の保全について、皆様のご理解とご協力をお
願いします。
聖なるガンジス川のようだ。
(和歌山を流れる川のあれこれ)
県内には、日本一長い二級河川も流れています。
それは、県の中央を流れる日高川(延長114,745
メートル)です。流域には、キャンプ場や竜神
温泉など多数の観光名所もあります。
一度訪ねてみては、いかがですか。

階段を降りてぶつぶつ川へ。

ぶつぶつ川到着。

水飲み場もあるよ!
と言ってもどこの水を飲んで良いのか
よくわからないでの今回はパス。

上流から流れてきて

どこかの川と合流し

橋を潜り

海まで到達。
二級河川ぶつぶつ川、全走破っ!
バイクの下へ戻ることに。

カンカンカンカン。踏切が。

紀勢本線、新宮行き。

さようなら~。

"ぶつぶつ"にちなんで、仏様を置いたら
縁起良さそう。と思いつつ見学完了。


近くの線路脇に駐車。
ちょっと歩く・・・

ぶつぶつ川入口到着。

二級河川 ぶつぶつ川:
ぶつぶつ川は、川の長さわずか13.5メートルの
日本一短い川です。
フツフツと清水が湧き出ていることから、昔から
そう呼ばれてきたそうです。今でも野菜や道具、
洗濯物を洗ったりと、生活に欠かせない貴重な水
源です。周辺の環境は、地元の方々の努力で維持
され、豊かな生物多様性が守られています。この
環境の保全について、皆様のご理解とご協力をお
願いします。
聖なるガンジス川のようだ。
(和歌山を流れる川のあれこれ)
県内には、日本一長い二級河川も流れています。
それは、県の中央を流れる日高川(延長114,745
メートル)です。流域には、キャンプ場や竜神
温泉など多数の観光名所もあります。
一度訪ねてみては、いかがですか。

階段を降りてぶつぶつ川へ。

ぶつぶつ川到着。

水飲み場もあるよ!
と言ってもどこの水を飲んで良いのか
よくわからないでの今回はパス。

上流から流れてきて

どこかの川と合流し

橋を潜り

海まで到達。
二級河川ぶつぶつ川、全走破っ!
バイクの下へ戻ることに。

カンカンカンカン。踏切が。

紀勢本線、新宮行き。

さようなら~。

"ぶつぶつ"にちなんで、仏様を置いたら
縁起良さそう。と思いつつ見学完了。
狼煙小学校跡地 [千葉からZ900RSと1000km超]
第一京丸 [千葉からZ900RSと1000km超]
11月上旬、和歌山に行った際に立ち寄った場所。


停められそうな場所へ。

太地町のくじら浜公園。
レリーフ、シャチじゃんと言うツッコミは・・・・


刃刺しの銅像。
俗にいう、クジラ漁の一番槍。
クジラ漁歓待 艦隊の総指揮者。
世襲制だけど、運命を握る人でもあったので
訓練は怠らなかったとの事。


第一京丸:
「第一京丸」は昭和46年(1971)に竣工された大型の
捕鯨船(キャッチャーボード)です。昭和46年(1971)
の第26次南氷洋捕鯨より参加し、商業捕鯨が国際的
に禁止されて以降は、鯨類捕獲調査(調査捕鯨)にお
いて活躍しました。平成19年(2007年)の第14次北
大西洋鯨類捕獲調査を最後に、捕鯨業を引退した
第一京丸ですが、町では共同船舶(株)からこの捕鯨
船を譲り受け、当くじら浜公園にて2012年より展示
しております。
(捕鯨船内部は、当時の様子を資料としてそのまま
保存しています。)

クロー(重さ3トン)
この大きなクローで、鯨の尾羽のつけ根を挟み、母船々尾
の鯨引揚げ斜路から解体甲板まで引揚げる時に使うものです。
洋上でのこの作業には大変な技術を要し、甲板長合図のもと
に熟知した甲板員の操作するウインチ(揚鯨機)3台によって
4人が一体となって作業に当たります。
このクロー掛けは中々の難業だといわれています。

船尾。

大迫力のスクリュー。

艦底。

(死の職場と言われている)第三艦橋はない。

船のこんなアングルも撮ることができたり。
海上に居る時はなかなか撮れない・・・・

鯨の怨念は付近におんねん。
と思いつつ見学完了。


停められそうな場所へ。

太地町のくじら浜公園。
レリーフ、シャチじゃんと言うツッコミは・・・・


刃刺しの銅像。
俗にいう、クジラ漁の一番槍。
クジラ漁
世襲制だけど、運命を握る人でもあったので
訓練は怠らなかったとの事。


第一京丸:
「第一京丸」は昭和46年(1971)に竣工された大型の
捕鯨船(キャッチャーボード)です。昭和46年(1971)
の第26次南氷洋捕鯨より参加し、商業捕鯨が国際的
に禁止されて以降は、鯨類捕獲調査(調査捕鯨)にお
いて活躍しました。平成19年(2007年)の第14次北
大西洋鯨類捕獲調査を最後に、捕鯨業を引退した
第一京丸ですが、町では共同船舶(株)からこの捕鯨
船を譲り受け、当くじら浜公園にて2012年より展示
しております。
(捕鯨船内部は、当時の様子を資料としてそのまま
保存しています。)

クロー(重さ3トン)
この大きなクローで、鯨の尾羽のつけ根を挟み、母船々尾
の鯨引揚げ斜路から解体甲板まで引揚げる時に使うものです。
洋上でのこの作業には大変な技術を要し、甲板長合図のもと
に熟知した甲板員の操作するウインチ(揚鯨機)3台によって
4人が一体となって作業に当たります。
このクロー掛けは中々の難業だといわれています。

船尾。

大迫力のスクリュー。

艦底。

(死の職場と言われている)第三艦橋はない。

船のこんなアングルも撮ることができたり。
海上に居る時はなかなか撮れない・・・・

鯨の怨念は付近におんねん。
と思いつつ見学完了。
熊野速玉神社 [千葉からZ900RSと1000km超]
八咫烏の聖地。


平日だけどバイク多い~。

表参道の鳥居。
進んで行くと・・・・

後白河法皇御撰梁塵秘抄所載。
熊野へ参るむは紀路と伊勢路とどれ近しどれ遠し
広大慈悲の道なれバ紀路も伊勢路も遠からず
さらに近くには国指定天然記念物
梛の大樹。
樹齢約千年との事。

本殿前の門。

こちらが本殿。
虎の絵馬と曼荼羅。
もうすぐで、絵馬は癸卯になるんだろうな。

御本尊様に御祈願。
「追突されませんように!」
続いて社務所へ。

実はこの神社、サッカーW杯に向けて
日本サッカー協会が御祈願に来た神社。
11月21日から、サッカーW杯カタール大会。

必勝祈願のサッカーお守り。
お守りGET。1000円(税込)。
自分以外誰も買っている人が居なかった。
あまり盛り上がっていない・・・・・のかも。
今月はW杯やで~。

私が日本代表必勝お守りを買ったけど、決して
グループリーグで敗退するフラグではないっ!
と思いつつ見学完了。


平日だけどバイク多い~。

表参道の鳥居。
進んで行くと・・・・

後白河法皇御撰梁塵秘抄所載。
熊野へ参るむは紀路と伊勢路とどれ近しどれ遠し
広大慈悲の道なれバ紀路も伊勢路も遠からず
さらに近くには国指定天然記念物
梛の大樹。
樹齢約千年との事。

本殿前の門。

こちらが本殿。
虎の絵馬と曼荼羅。
もうすぐで、絵馬は癸卯になるんだろうな。

御本尊様に御祈願。
「追突されませんように!」
続いて社務所へ。

実はこの神社、サッカーW杯に向けて
日本サッカー協会が御祈願に来た神社。
11月21日から、サッカーW杯カタール大会。

必勝祈願のサッカーお守り。
お守りGET。1000円(税込)。
自分以外誰も買っている人が居なかった。
あまり盛り上がっていない・・・・・のかも。
今月はW杯やで~。

私が日本代表必勝お守りを買ったけど、決して
グループリーグで敗退するフラグではないっ!
と思いつつ見学完了。
潮岬 [千葉からZ900RSと1000km超]
本州最南端。

端っこにはバイク仲間が集まると。

駐車場へ。

本州最南端のキャンプ場。
平日だったけどキャンパーが結構居た。

早速、本州最南端へ。

本州最南端の碑に到着っ!

でも、有名なのはこっちか。

さらにこんな説明板も。
潮岬望楼の芝焼き:
吉野熊野国立公園内に位置するこの場所には、昔、海軍の
望楼(物見櫓)があったことから「望楼の芝」とも呼ばれて
います。
枯れた芝を焼き払い、害虫駆除とともに新芽発育を促すこ
とを目的として昔から行われていた芝焼きは、現在では
「本州最南端の火祭り」として毎年1月最終土曜日の夜に
開催されています。目の前に広がる***(判読不能)m2の
(読めない)上パノラマは、周囲に咲く水仙と共に紀南に
春を告げる一大イベントとなっています。

下村宏の像。
玉音放送の時の内閣情報局総裁。
説明文はあったけど、こちらも読めない。
なんか号の海南とかけているっぽい感じ。

続いて、潮岬観光タワーへ。

本州最南端のポスト。

300円払い中へ。
この顔出しパネルで記念撮影する人
居るのかな?

タワー内は1階と7階のみ。

7階到着。

フジカラーのベンチにて

本州最南端訪問証明書。
入場券と兼ねている。

最上階へ。

本州最南端 潮岬。
その先を航行するのは・・・・・

オーシャン東九フェリー(東京~徳島)の
フェリーしまんと。
展望台から更に1階に下りると

海難1890の展示が。

これは激中で使用されていた井戸との事。

最南端行ったので、最北端・最東端・最西端
に行っていつかは制覇したいなー。
と思いつつ見学完了。

端っこにはバイク仲間が集まると。

駐車場へ。

本州最南端のキャンプ場。
平日だったけどキャンパーが結構居た。

早速、本州最南端へ。

本州最南端の碑に到着っ!

でも、有名なのはこっちか。

さらにこんな説明板も。
潮岬望楼の芝焼き:
吉野熊野国立公園内に位置するこの場所には、昔、海軍の
望楼(物見櫓)があったことから「望楼の芝」とも呼ばれて
います。
枯れた芝を焼き払い、害虫駆除とともに新芽発育を促すこ
とを目的として昔から行われていた芝焼きは、現在では
「本州最南端の火祭り」として毎年1月最終土曜日の夜に
開催されています。目の前に広がる***(判読不能)m2の
(読めない)上パノラマは、周囲に咲く水仙と共に紀南に
春を告げる一大イベントとなっています。

下村宏の像。
玉音放送の時の内閣情報局総裁。
説明文はあったけど、こちらも読めない。
なんか号の海南とかけているっぽい感じ。

続いて、潮岬観光タワーへ。

本州最南端のポスト。

300円払い中へ。
この顔出しパネルで記念撮影する人
居るのかな?

タワー内は1階と7階のみ。

7階到着。

フジカラーのベンチにて

本州最南端訪問証明書。
入場券と兼ねている。

最上階へ。

本州最南端 潮岬。
その先を航行するのは・・・・・

オーシャン東九フェリー(東京~徳島)の
フェリーしまんと。
展望台から更に1階に下りると

海難1890の展示が。

これは激中で使用されていた井戸との事。

最南端行ったので、最北端・最東端・最西端
に行っていつかは制覇したいなー。
と思いつつ見学完了。
紀伊有田駅 [千葉からZ900RSと1000km超]
鳥海山大物忌神社 [千葉からZ900RSと1000km超]
7月中旬、山形に行った際に立ち寄った場所。


駐車場へ。

拝殿か幣殿。本殿ではない。

神宮大麻をおまつりしましょう。
ハァ、ハァ、ハァ、ハァ・・・・・・

社務所には色々なお守りが。
でも、朝早すぎてやっていない。
本殿へ。

うっ!。すごい階段・・・・・・・

ハァ、ハァ、ハァ、ハァ、到着っ!

鳥海山大物忌神社:
本境内の一番奥、最高所に大物忌神を祀る大物忌神社本殿(東側)
月山神を祀る摂社月山神社本殿(西側)が南面して並び立っている。
前身の本殿が宝永三年(1706)正月の火災で焼失し、宝永八年(1711)
に庄内藩酒井家によって、現本殿が再建されたと伝わる。本殿
後ろの斜面に石段が残っており、鳥海山詣りの道者たちは、この
石段を通り、山に向かったと言われている。
両社殿は、彫刻や脇障子の絵柄を除けば、全く同型、同大の一間
社流造の建築である。もとは屋根が茅葺であったが、昭和三八年
(1963)の千四百年祭の際、銅板に葺き替えられた。昭和十四年
(1939)に壁板や土台を取り替え、屋根を葺き替えるなど修理され
併せて周囲の中門廻廊や玉垣が造り替えられている。続いて中門
の下方には、戦時下の昭和十八年(1943)に、台湾産檜材を用いて
桁行五間、梁間三間の拝殿を建て、登廊で繋がれた。これら昭和
戦前期建造物の設計は、東京小石川区の小林設計事務所小林謙一
が担当した。江戸中期の地方色のある両本殿と、近代の端正な設
計の拝殿等が破綻なく融和しているのは、設計者が内務省神社局
宮内省内匠寮の設計者の系譜に連なり、神社建築の設計手法に通
じていたことをうかがわせる。
周囲のタブノキや杉の社叢とあいまって、かつて「出羽國一宮両
所宮」とも称され、明治以降「国弊中社」に格付けされた大神の
社殿としての風格が感じられる。
ハァ、ハァ、ハァ、ハァ・・・・長い。
小石川区なんてあったんだー。

両社殿は見えない。
これ以上先に行けない。

御祈願を。
「追突されませんように!」

鳥海山のご加護を頂き見学完了。


駐車場へ。

拝殿か幣殿。本殿ではない。

神宮大麻をおまつりしましょう。
ハァ、ハァ、ハァ、ハァ・・・・・・

社務所には色々なお守りが。
でも、朝早すぎてやっていない。
本殿へ。

うっ!。すごい階段・・・・・・・

ハァ、ハァ、ハァ、ハァ、到着っ!

鳥海山大物忌神社:
本境内の一番奥、最高所に大物忌神を祀る大物忌神社本殿(東側)
月山神を祀る摂社月山神社本殿(西側)が南面して並び立っている。
前身の本殿が宝永三年(1706)正月の火災で焼失し、宝永八年(1711)
に庄内藩酒井家によって、現本殿が再建されたと伝わる。本殿
後ろの斜面に石段が残っており、鳥海山詣りの道者たちは、この
石段を通り、山に向かったと言われている。
両社殿は、彫刻や脇障子の絵柄を除けば、全く同型、同大の一間
社流造の建築である。もとは屋根が茅葺であったが、昭和三八年
(1963)の千四百年祭の際、銅板に葺き替えられた。昭和十四年
(1939)に壁板や土台を取り替え、屋根を葺き替えるなど修理され
併せて周囲の中門廻廊や玉垣が造り替えられている。続いて中門
の下方には、戦時下の昭和十八年(1943)に、台湾産檜材を用いて
桁行五間、梁間三間の拝殿を建て、登廊で繋がれた。これら昭和
戦前期建造物の設計は、東京小石川区の小林設計事務所小林謙一
が担当した。江戸中期の地方色のある両本殿と、近代の端正な設
計の拝殿等が破綻なく融和しているのは、設計者が内務省神社局
宮内省内匠寮の設計者の系譜に連なり、神社建築の設計手法に通
じていたことをうかがわせる。
周囲のタブノキや杉の社叢とあいまって、かつて「出羽國一宮両
所宮」とも称され、明治以降「国弊中社」に格付けされた大神の
社殿としての風格が感じられる。
ハァ、ハァ、ハァ、ハァ・・・・長い。
小石川区なんてあったんだー。

両社殿は見えない。
これ以上先に行けない。

御祈願を。
「追突されませんように!」

鳥海山のご加護を頂き見学完了。
安平駅 [千葉からZ900RSと1000km超]
8月中旬、北海道に行った際に立ち寄った場所。


駅前に駐車。もう、停め放題っ!
早速、駅舎内へ。

駅ノートあるよ。

室蘭線 鉄道遺産。
おお、すげー。かっこいい。
いずれ行きたいなー。

あっ!・・・・・・・

上下それぞれ8本/日。
但し、朝早くから夜遅くまで電車が来たり。
意外と便利かも。

隣の駅まで一番安くて250円。

駅間所要時間。苫小牧まで、28分。
大体(総武線快速で)、船橋から東京までの所要時間と同じ。

地図上だと隣町。
北海道広い。
ホームへ。
もちろん、改札などない。

駅標名。意外に新しい。
見渡す限り、雑木林な風景。

室蘭本線が廃線になる前に、またこの辺りの
駅に来られると良いなー。
と思いつつ見学完了。


駅前に駐車。もう、停め放題っ!
早速、駅舎内へ。

駅ノートあるよ。

室蘭線 鉄道遺産。
おお、すげー。かっこいい。
いずれ行きたいなー。

あっ!・・・・・・・

上下それぞれ8本/日。
但し、朝早くから夜遅くまで電車が来たり。
意外と便利かも。

隣の駅まで一番安くて250円。

駅間所要時間。苫小牧まで、28分。
大体(総武線快速で)、船橋から東京までの所要時間と同じ。

地図上だと隣町。
北海道広い。
ホームへ。
もちろん、改札などない。

駅標名。意外に新しい。
見渡す限り、雑木林な風景。

室蘭本線が廃線になる前に、またこの辺りの
駅に来られると良いなー。
と思いつつ見学完了。
帆立岩 [千葉からZ900RSと1000km超]
9月中旬、石川に行った際に立ち寄った場所。


停められそうな場所へ。

サンゴっぽい岩が。

さらにその先に・・・・・

帆立岩。

帆立岩:
帆立岩は、新第三期中新世代(約2000万年前)海底噴火
でできた凝灰岩が、時代を経て、引き波の浸食作用に
よって陸地側がえぐられたもので、舟が帆を立てた姿
に似ていることから、このように命名されました。
もとは波うちぎわにありましたが、浸食がひどくなり
その形状保存のため、現在地に移したものです。
帆を立てる帆立なのね。

こっちのホタテじゃないんだ。

とっても海とマッチした岩。

ここからさらに上の方にも帆立岩。

帆立岩の本音は「海の底に戻りたいよ~」
だったり。と思いつつ見学完了。


停められそうな場所へ。

サンゴっぽい岩が。

さらにその先に・・・・・

帆立岩。

帆立岩:
帆立岩は、新第三期中新世代(約2000万年前)海底噴火
でできた凝灰岩が、時代を経て、引き波の浸食作用に
よって陸地側がえぐられたもので、舟が帆を立てた姿
に似ていることから、このように命名されました。
もとは波うちぎわにありましたが、浸食がひどくなり
その形状保存のため、現在地に移したものです。
帆を立てる帆立なのね。

こっちのホタテじゃないんだ。

とっても海とマッチした岩。

ここからさらに上の方にも帆立岩。

帆立岩の本音は「海の底に戻りたいよ~」
だったり。と思いつつ見学完了。
辯天宗御廟 [千葉からZ900RSと1000km超]
柿博物館 [千葉からZ900RSと1000km超]
10月上旬、奈良に行った際に立ち寄った場所。


駐車場へ。後ろに柿が!

正式には奈良県農業研究開発センター内の
柿博物館。
研究開発センターなだけあって
ちゃんと柿の木も。

柿博物館。

柿博物館の隣の緑、実は上から
見ると柿の葉になっていると言う。

早速、入場。無料っ!

柿渋染め。良い色だー。
この題字の木も、ひそかに柿の木。
柿の品種特性。
完全甘柿・・・果実中に種子が入らなくても樹上で自然に甘くなる
不完全甘柿・・果実中に種子が沢山入ると、全体に渋が抜ける
完全渋柿・・・果実中に種子が入っても入らなくても渋いまま
熟柿になると甘くなる。
不完全渋柿・・果実中に種子が入ると、種子のごく近い部分だけ掲斑
が入り渋が抜けるが、全体は渋い。
柿の失敗作が渋柿ではないみたい。
渋い渋くないは品種によるっぽい。
等級・階級印。
昔の階級は、特天(4L)・天(3L)・飛(2L)・特(L)
・松(M)・竹(S)・梅(2S)と並んでいたらしい。
階級=大きさなのね~。
この後、係の人から
「ビデオみますか?」
と聞かれたので15分の視聴。
柿の栽培方法の解説は参考になった。
剪定→適蕾→適果を経て出荷。
出荷される柿はエリート中のエリート。

全国の柿キャラクターを見て

柿博物館退出っ!
バイクのシートに乗っているのは・・・・・

博物館館内で売っていた柿。
5個入り300円(税込)。
スーパーで買うより安い。

持ち帰って、家で実食。
う、う、う、うまい。水っぽくない、柿の味が凝縮
された感じ。しかも、皮ごと食べられる~。

完食っっっっっ!!!!!
柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺。
ゴーン、ゴーン、ゴーン、ゴーン、ゴーン。


駐車場へ。後ろに柿が!

正式には奈良県農業研究開発センター内の
柿博物館。
研究開発センターなだけあって
ちゃんと柿の木も。

柿博物館。

柿博物館の隣の緑、実は上から
見ると柿の葉になっていると言う。

早速、入場。無料っ!

柿渋染め。良い色だー。
この題字の木も、ひそかに柿の木。
柿の品種特性。
完全甘柿・・・果実中に種子が入らなくても樹上で自然に甘くなる
不完全甘柿・・果実中に種子が沢山入ると、全体に渋が抜ける
完全渋柿・・・果実中に種子が入っても入らなくても渋いまま
熟柿になると甘くなる。
不完全渋柿・・果実中に種子が入ると、種子のごく近い部分だけ掲斑
が入り渋が抜けるが、全体は渋い。
柿の失敗作が渋柿ではないみたい。
渋い渋くないは品種によるっぽい。
等級・階級印。
昔の階級は、特天(4L)・天(3L)・飛(2L)・特(L)
・松(M)・竹(S)・梅(2S)と並んでいたらしい。
階級=大きさなのね~。
この後、係の人から
「ビデオみますか?」
と聞かれたので15分の視聴。
柿の栽培方法の解説は参考になった。
剪定→適蕾→適果を経て出荷。
出荷される柿はエリート中のエリート。

全国の柿キャラクターを見て

柿博物館退出っ!
バイクのシートに乗っているのは・・・・・

博物館館内で売っていた柿。
5個入り300円(税込)。
スーパーで買うより安い。

持ち帰って、家で実食。
う、う、う、うまい。水っぽくない、柿の味が凝縮
された感じ。しかも、皮ごと食べられる~。

完食っっっっっ!!!!!
柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺。
ゴーン、ゴーン、ゴーン、ゴーン、ゴーン。
接吻トンネル [千葉からZ900RSと1000km超]
9月中旬、石川に行った際に立ち寄った場所。


駐車場に到着。
その駐車場には・・・・

麒山和尚が建立した石仏。

能登の難所をひらいたーーーー
麒山(きざん)和尚が建立した石仏
現在の輪島市曽々木から珠洲市真浦にいたる断崖絶壁
の地は、昔は道も無く「能登親知らず」とか「ヒロギ
の険」とおそれられた難所でした。手をひろげ、岩に
つかまって渡る途中、あやまって海に落ちて失命する
人が毎年あとを絶たなかったーと語り伝えられています。
安永9年(1780)、海蔵寺八世の麒山瑞麟(きざんずいりん)
和尚が開道を決意。加越能三国を托鉢して浄財を集め、
13年後の寛政4年(1792)に、この絶壁にひとすじの道
を通しました。以来、人々は親しく「八世の和尚さん」
と呼び、その徳を語り継いできました。
この石仏は開道記念に、往来人の安全を祈念して、
麒山和尚が建てたものです。

「追突されませんように!」

接吻トンネルへ。

接吻トンネルの前「福が穴」を潜ると

岩窟不動。

内部は申し訳程度の照明。
奥は真っ暗。

フラッシュじゃー。
「追突されませんように!」

続いて接吻トンネルへ。

映画「忘却の花びら」(昭和32年東宝映画) あらまし
終戦直後、一宮葵(草笛光子さん)は満州で敵兵に汚された
恋人の藤崎克己(小泉博さん)から姿を消した。葵の妹鮎子
(司 葉子さん)が能登から姉の日記を鎌倉に住む克己のもと
へ届けたとき互いに惹かれるものがあった。その後、克己
は鮎子への思慕に能登に訪れるが親に冷たく断られて、能
登の名所親不知に出かけたところ、黄昏のトンネルで思い
がけず鮎子と出逢い、二人はひしと抱き合った。仲を引き
裂こうとする多くの試練を乗り越え、強く愛し合う二人を
見て、葵は自分の恋を忘却の彼方に捨て去るのでした。
愛する二人が接吻した黄昏のトンネル
↓
せっぷんとんねる。
恋がかなうかも?!

手掘りのトンネル。

照明はあるけど申し訳程度。

ここから見る黄昏の夕日はキレイだろうな。
そしてその二人を見ている葵さんは・・・・

葵さんは俺の嫁っ!
と思いつつ見学完了。


駐車場に到着。
その駐車場には・・・・

麒山和尚が建立した石仏。

能登の難所をひらいたーーーー
麒山(きざん)和尚が建立した石仏
現在の輪島市曽々木から珠洲市真浦にいたる断崖絶壁
の地は、昔は道も無く「能登親知らず」とか「ヒロギ
の険」とおそれられた難所でした。手をひろげ、岩に
つかまって渡る途中、あやまって海に落ちて失命する
人が毎年あとを絶たなかったーと語り伝えられています。
安永9年(1780)、海蔵寺八世の麒山瑞麟(きざんずいりん)
和尚が開道を決意。加越能三国を托鉢して浄財を集め、
13年後の寛政4年(1792)に、この絶壁にひとすじの道
を通しました。以来、人々は親しく「八世の和尚さん」
と呼び、その徳を語り継いできました。
この石仏は開道記念に、往来人の安全を祈念して、
麒山和尚が建てたものです。

「追突されませんように!」

接吻トンネルへ。

接吻トンネルの前「福が穴」を潜ると

岩窟不動。

内部は申し訳程度の照明。
奥は真っ暗。

フラッシュじゃー。
「追突されませんように!」

続いて接吻トンネルへ。

映画「忘却の花びら」(昭和32年東宝映画) あらまし
終戦直後、一宮葵(草笛光子さん)は満州で敵兵に汚された
恋人の藤崎克己(小泉博さん)から姿を消した。葵の妹鮎子
(司 葉子さん)が能登から姉の日記を鎌倉に住む克己のもと
へ届けたとき互いに惹かれるものがあった。その後、克己
は鮎子への思慕に能登に訪れるが親に冷たく断られて、能
登の名所親不知に出かけたところ、黄昏のトンネルで思い
がけず鮎子と出逢い、二人はひしと抱き合った。仲を引き
裂こうとする多くの試練を乗り越え、強く愛し合う二人を
見て、葵は自分の恋を忘却の彼方に捨て去るのでした。
愛する二人が接吻した黄昏のトンネル
↓
せっぷんとんねる。
恋がかなうかも?!

手掘りのトンネル。

照明はあるけど申し訳程度。

ここから見る黄昏の夕日はキレイだろうな。
そしてその二人を見ている葵さんは・・・・

葵さんは俺の嫁っ!
と思いつつ見学完了。
蕪島 [千葉からZ900RSと1000km超]
8月中旬、北海道行く前に八戸に寄った際に立ち寄った場所。


駐車場へ。

早速、蕪島へ。

途中、ウミネコ。

ここは国指定天然記念物
蕪島ウミネコ繁殖地。

ウミネコ観察に際しての注意事項。

望遠にて。ウミネコっ!

蕪島に到着。

ウミネコの狛犬。

手水もウミネコ。

こちらは本殿。でかいっ!
「追突されませんように!」

おみくじもウミネコ。

うーむ、吉。微妙・・・・・
今は刺激のないとき。だからといって新しい事に
手を出す時期ではありません。現状維持が成功の
カギとなるでしょう。一日一日を大切に過ごせば
よい方向に向かうでしょう。
現状維持が一番っ!
良く見ると、神社をぐるぐる回っている人多数。

これかー。
実はこの時、説明を良く読んでなく1周しかしなかった。
だから、この後の北海道では天気が悪かったのかも。

蕪島だけにカブなのかな?

手に持っているのはうんこ?
鳥が多いので糞を持っていると言うことかな?
外周しているとこんな碑が。
海防艦 稲木。

昭和二十年八月九日八戸港内に仮泊中の海防艦稲木は
来襲せる米三十八機動部隊の艦載機群と交戦勇戦敢闘
遂に沈没す。
爾来三十八年当時の乗組員並びにその父母二世及び関
係者相図り記念碑を建立して物故者の霊を追悼しあわ
せて世界の恒久平和を祈念するものである。

稲木はウミネコと八戸港を守った軍神っ!
と思いつつ見学完了。


駐車場へ。

早速、蕪島へ。

途中、ウミネコ。

ここは国指定天然記念物
蕪島ウミネコ繁殖地。

ウミネコ観察に際しての注意事項。

望遠にて。ウミネコっ!

蕪島に到着。

ウミネコの狛犬。

手水もウミネコ。

こちらは本殿。でかいっ!
「追突されませんように!」

おみくじもウミネコ。

うーむ、吉。微妙・・・・・
今は刺激のないとき。だからといって新しい事に
手を出す時期ではありません。現状維持が成功の
カギとなるでしょう。一日一日を大切に過ごせば
よい方向に向かうでしょう。
現状維持が一番っ!
良く見ると、神社をぐるぐる回っている人多数。

これかー。
実はこの時、説明を良く読んでなく1周しかしなかった。
だから、この後の北海道では天気が悪かったのかも。

蕪島だけにカブなのかな?

手に持っているのはうんこ?
鳥が多いので糞を持っていると言うことかな?
外周しているとこんな碑が。
海防艦 稲木。

昭和二十年八月九日八戸港内に仮泊中の海防艦稲木は
来襲せる米三十八機動部隊の艦載機群と交戦勇戦敢闘
遂に沈没す。
爾来三十八年当時の乗組員並びにその父母二世及び関
係者相図り記念碑を建立して物故者の霊を追悼しあわ
せて世界の恒久平和を祈念するものである。

稲木はウミネコと八戸港を守った軍神っ!
と思いつつ見学完了。
林橋 [千葉からZ900RSと1000km超]
羽後三埼灯台 [千葉からZ900RSと1000km超]
7月中旬、山形に行った際に立ち寄った場所。
秋田だけど・・・


駐車場へ。

三崎公園内にある灯台。

まだ、アジサイの咲いている頃。

日本海な崖の道を登っていく・・・・

帰り道、マムシに遭遇したのはこの公園(参照)。


奥の細道の笹トンネルを抜けると・・・・

三埼灯台の標識が!

近くには太子堂とタブノキ。
さらに戊辰戦争の戦没者碑が。
心霊スポットではない・・・

羽後三埼灯台に到着っ!
ロープが張ってあるのでこれ以上は進めない。

白亜な灯台。
でも、天気が悪くて黒っぽく見える。

見えるマムシは動きが遅いので怖くないっ!
と思いつつ見学完了。
秋田だけど・・・


駐車場へ。

三崎公園内にある灯台。

まだ、アジサイの咲いている頃。

日本海な崖の道を登っていく・・・・

帰り道、マムシに遭遇したのはこの公園(参照)。


奥の細道の笹トンネルを抜けると・・・・

三埼灯台の標識が!

近くには太子堂とタブノキ。
さらに戊辰戦争の戦没者碑が。
心霊スポットではない・・・

羽後三埼灯台に到着っ!
ロープが張ってあるのでこれ以上は進めない。

白亜な灯台。
でも、天気が悪くて黒っぽく見える。

見えるマムシは動きが遅いので怖くないっ!
と思いつつ見学完了。
平時忠一族の墳 [千葉からZ900RSと1000km超]
珠洲市の山中にひっそりと。


駐車場に到着。

源義経と平時忠~仇敵を超越した義親子の絆~
文治元年(一一八五)三月の壇ノ浦の戦いで敗れ、囚われ
の身となった平時忠は、半年後の九月に能登へ流された。
時忠は現在の珠洲市大谷町に辿り着き、付近にしばらく
滞在した後、平家の守り神であるカラスに導かれて川を
さかのぼり、上流の静かな土地(大谷町則貞)に居を構えた。
以後、北嶋荒御前神社や吉祥寺の元地・古屋などを訪ね
歌などを残した。
「白波の打ち驚かす岩の上に寝らえで松の幾世経ぬらん」
これは時忠が配流地で、波に洗われる岩間に生えた松を
我が身にたとえて詠んだ歌である。左記の歌碑がそれで
ある。その時忠の娘が、源義経の妻であったことから、
義経は奥州へ向かう際、義理の父・時忠を訪ねるために
珠洲に立ち寄ったのである。こうした仇敵を超越した義
親子の絆の深さは、今もなお語り継がれている。

さらに近くには能登平家物語の絵巻が。

平清盛と同じ時代を生き
「平家に非ずんば人に非ず」
と豪語した"平大納言時忠"

「白波の打ち驚かす岩の上に寝らえで松の幾世経ぬらん」
の隣の階段を下りて一族の墳へ。

はぁ、はぁ、はぁ、はぁ・・・・

ん!?。進んでみる。

平氏の家紋が。

到着っ!

平一族墓所:
時忠卿甲子年卯月廿四日御逝去に依り
この地にて葬る。先代を偲び墓所に
石碑を建立する。
時忠卿は此の地に配流後後妻を娶り一子
を授かり子に源氏の監視を和らげる為
姓を則貞(規律順守)と改め健康を願い
時康と命名。

もし、時忠卿が今の時代バイク乗りになっていたら・・・
「Araiに非ずんばヘルメットに非ず」
と言っていたかも。
※注、時忠卿のお言葉です。

実際のお墓はこちら。
鍵がかかっていて中には入れない・・・

扉越しから。
一番手前の大きいのが時忠卿のお墓。


一族を滅ぼされ、娘も殺され、婿さんも
殺され、もしかしたら恨みはあったかも・・・
と思いつつ見学完了。


駐車場に到着。

源義経と平時忠~仇敵を超越した義親子の絆~
文治元年(一一八五)三月の壇ノ浦の戦いで敗れ、囚われ
の身となった平時忠は、半年後の九月に能登へ流された。
時忠は現在の珠洲市大谷町に辿り着き、付近にしばらく
滞在した後、平家の守り神であるカラスに導かれて川を
さかのぼり、上流の静かな土地(大谷町則貞)に居を構えた。
以後、北嶋荒御前神社や吉祥寺の元地・古屋などを訪ね
歌などを残した。
「白波の打ち驚かす岩の上に寝らえで松の幾世経ぬらん」
これは時忠が配流地で、波に洗われる岩間に生えた松を
我が身にたとえて詠んだ歌である。左記の歌碑がそれで
ある。その時忠の娘が、源義経の妻であったことから、
義経は奥州へ向かう際、義理の父・時忠を訪ねるために
珠洲に立ち寄ったのである。こうした仇敵を超越した義
親子の絆の深さは、今もなお語り継がれている。

さらに近くには能登平家物語の絵巻が。

平清盛と同じ時代を生き
「平家に非ずんば人に非ず」
と豪語した"平大納言時忠"

「白波の打ち驚かす岩の上に寝らえで松の幾世経ぬらん」
の隣の階段を下りて一族の墳へ。

はぁ、はぁ、はぁ、はぁ・・・・

ん!?。進んでみる。

平氏の家紋が。

到着っ!

平一族墓所:
時忠卿甲子年卯月廿四日御逝去に依り
この地にて葬る。先代を偲び墓所に
石碑を建立する。
時忠卿は此の地に配流後後妻を娶り一子
を授かり子に源氏の監視を和らげる為
姓を則貞(規律順守)と改め健康を願い
時康と命名。

もし、時忠卿が今の時代バイク乗りになっていたら・・・
「Araiに非ずんばヘルメットに非ず」
と言っていたかも。
※注、時忠卿のお言葉です。

実際のお墓はこちら。
鍵がかかっていて中には入れない・・・

扉越しから。
一番手前の大きいのが時忠卿のお墓。


一族を滅ぼされ、娘も殺され、婿さんも
殺され、もしかしたら恨みはあったかも・・・
と思いつつ見学完了。
禄剛埼灯台 [千葉からZ900RSと1000km超]
能登半島のさいはて。


駐車場へ。

尚、駐車場は道の駅 狼煙。

近くにはさいはて資料館も。
当日、やっていなかった・・・・

灯台まで365m。

但し、ひたすら坂っ!
最近の関東では考えられないほどの暑さ。
密かにヤバかった。

途中、こんなのも。
坂の一番下からレンタルできればいいのに。

日本列島ここが中心。

中心の中心に立つ!

ウラジオストック772kmの看板。

ウラジオストックー。
くぅ、天気悪いのか見えない・・・・・

佐渡ヶ島ー。
これも、天気が悪いのか見えない・・・・

禄剛埼灯台に到着。

禄剛埼灯台:
この灯台は明治16年(1883年)、日本への技術指導にきていた
イギリス人の設計により建設されたものです。当時は灯油で
発光していましたが、昭和15年に電化され、その光は
海上34kmまで達します。
古来この地は日本海を航海する人にとって重要な目印で、江
戸時代にはこの真近にある山伏山の山腹に九尺四方の行燈を
設け、毎夜灯火して夜間航海の目印としていました。
また天保7年(1836年)には海上警備のため、現在の灯台付近に
砲台が築かれていました。
なおこの灯台は昭和38年まで灯台守が常駐していましたが、
現在は無人灯台になっています。

昔は灯油で発行 発光していたのかー。

とっても綺麗な灯台。
観光地化されているのでメンテナンス
(掃除とか)も良くされているんだろうな。


こういうのは見えなくても良かったのに・・・・
ウラジオストックや佐渡ヶ島を見たかった。
と思いつつ見学完了。


駐車場へ。

尚、駐車場は道の駅 狼煙。

近くにはさいはて資料館も。
当日、やっていなかった・・・・

灯台まで365m。

但し、ひたすら坂っ!
最近の関東では考えられないほどの暑さ。
密かにヤバかった。

途中、こんなのも。
坂の一番下からレンタルできればいいのに。

日本列島ここが中心。

中心の中心に立つ!

ウラジオストック772kmの看板。

ウラジオストックー。
くぅ、天気悪いのか見えない・・・・・

佐渡ヶ島ー。
これも、天気が悪いのか見えない・・・・

禄剛埼灯台に到着。

禄剛埼灯台:
この灯台は明治16年(1883年)、日本への技術指導にきていた
イギリス人の設計により建設されたものです。当時は灯油で
発光していましたが、昭和15年に電化され、その光は
海上34kmまで達します。
古来この地は日本海を航海する人にとって重要な目印で、江
戸時代にはこの真近にある山伏山の山腹に九尺四方の行燈を
設け、毎夜灯火して夜間航海の目印としていました。
また天保7年(1836年)には海上警備のため、現在の灯台付近に
砲台が築かれていました。
なおこの灯台は昭和38年まで灯台守が常駐していましたが、
現在は無人灯台になっています。

昔は灯油で

とっても綺麗な灯台。
観光地化されているのでメンテナンス
(掃除とか)も良くされているんだろうな。


こういうのは見えなくても良かったのに・・・・
ウラジオストックや佐渡ヶ島を見たかった。
と思いつつ見学完了。
葦毛崎展望台 [千葉からZ900RSと1000km超]
8月中旬、北海道に行く途中の八戸で立ち寄った場所。

JR東日本のポスターにもなっている場所。

毎度おなじみ雨の中、駐車場へ。

早速、展望台へ。

葦毛崎展望台到着。

葦毛崎展望台:
変った形の展望台は、戦時中に海軍の監視所
として使われていました。周辺では、春から
秋にかけて様々な花が楽しめます。
種差海岸随一の展望スポットです。

監視所の土台だったのかな?
砲台の台座っぽい気も。

ここから約230km先に苫小牧市が・・・

天気が悪くて見えない。

この展望台、下から見上げると
中世ヨーロッパの城郭みたい。

ここから見る日の出はキレイだろうな~。

ロシア軍が侵攻してきても、ここで
発見して食い止められるかも。
と思いつつ見学完了。

JR東日本のポスターにもなっている場所。

毎度おなじみ雨の中、駐車場へ。

早速、展望台へ。

葦毛崎展望台到着。

葦毛崎展望台:
変った形の展望台は、戦時中に海軍の監視所
として使われていました。周辺では、春から
秋にかけて様々な花が楽しめます。
種差海岸随一の展望スポットです。

監視所の土台だったのかな?
砲台の台座っぽい気も。

ここから約230km先に苫小牧市が・・・

天気が悪くて見えない。

この展望台、下から見上げると
中世ヨーロッパの城郭みたい。

ここから見る日の出はキレイだろうな~。

ロシア軍が侵攻してきても、ここで
発見して食い止められるかも。
と思いつつ見学完了。
十六羅漢岩 [千葉からZ900RSと1000km超]
7月中旬、山形に行った際に立ち寄った場所。


駐車場へ。

裏に見える建物はレストラン。
夕日ラーメンが名物。

名勝羅漢岩の由来:
現曹洞宗海禪寺 二十一代目の石川寛海大和尚が
日本海の荒波の打ち寄せる奇岩の連る数百メー
トルに点綴して刻んだ、十六羅漢がある。
奇岩怪岩に富んだこの岩石を利用して巧に佛像
二十二体を彫刻した和尚の努力と精進の程に敬
虔の念を捧げます。又和尚は作佛発願以来喜捨
金を酒田に托鉢し、一両を求めると一佛を刻し
元治元年より明治初年までの間石工と共に彫刻
したのが羅漢像である。
正面に釈迦・文殊・普賢の三尊と、その周囲に
十六羅漢その他の佛像を配し全部半身佛である。
像は岩形に応じその姿態を羅漢にしたのは自然
の景観に一段の奇観を添え接する人々の庶民信
仰を培う和尚の慈悲心の現れである。

十六羅漢岩へ。

ん!?これは・・・・・

見なかったことにしよう。

階段・坂を下りて行くと

羅漢様が!さらに海沿いへ。

おおー。すげー羅漢岩。

ラシュモア山に来た気分に。

結構、表情豊かに彫られている~。
羅漢岩の後は、近くにある出羽二見へ。



駐車場へ。

裏に見える建物はレストラン。
夕日ラーメンが名物。

名勝羅漢岩の由来:
現曹洞宗海禪寺 二十一代目の石川寛海大和尚が
日本海の荒波の打ち寄せる奇岩の連る数百メー
トルに点綴して刻んだ、十六羅漢がある。
奇岩怪岩に富んだこの岩石を利用して巧に佛像
二十二体を彫刻した和尚の努力と精進の程に敬
虔の念を捧げます。又和尚は作佛発願以来喜捨
金を酒田に托鉢し、一両を求めると一佛を刻し
元治元年より明治初年までの間石工と共に彫刻
したのが羅漢像である。
正面に釈迦・文殊・普賢の三尊と、その周囲に
十六羅漢その他の佛像を配し全部半身佛である。
像は岩形に応じその姿態を羅漢にしたのは自然
の景観に一段の奇観を添え接する人々の庶民信
仰を培う和尚の慈悲心の現れである。

十六羅漢岩へ。

ん!?これは・・・・・

見なかったことにしよう。

階段・坂を下りて行くと

羅漢様が!さらに海沿いへ。

おおー。すげー羅漢岩。

ラシュモア山に来た気分に。

結構、表情豊かに彫られている~。
羅漢岩の後は、近くにある出羽二見へ。

あつみ山や吹浦かけて夕涼み

芭蕉も絶賛した(かもしれない)二見岩。

松尾芭蕉が(酒田に)来ていた時、石川寛海大和尚
が居たら、きっと岩に芭蕉が彫られたかも。
と思いつつ見学完了。
アゼチの岬 [千葉からZ900RSと1000km超]
8月、北海道に行った際に立ち寄った場所。


駐車場に到着。真っ白っ!

岬の場所はこの辺。
早速、アゼチの岬へ。

入口。

アゼチの岬:
アゼチの岬はイ琵琶瀬湾(びわせわん)に突き出た岬で、小島・ゴメ島
嶮暮帰島(けんぼっきとう)を望め、遥かに琵琶瀬湾(びわせわん)、
浜中湾の海岸線を見渡すことができ、真夏の落 日は素晴らしいもの
です。海鳥の聖地となる小さな島や岩があり、多くの海鳥が生息し、
浜中町の鳥「エトピリカ」が営巣します。

霧多布岬と同じく、ここにもAR SPOT。

石川五右ェ門登場。

遊歩道を歩いて行くと・・・・

アゼチの岬到着っ!

て、天気が・・・・・
嶮暮帰島、ここから見たかった。
この後、厚岸に行く途中で見たけど。

「どんべえ」に会えなかったけどルパンに
会えたからヨシ。と思いつつ見学完了。
この後、浜中町総合文化センター内にある
モンキー・パンチ・コレクションへ。

到着っ!
な、なんと、お盆で休館。

「ヤツはとんでもないものを盗んでいきました。
北海道ツーリングの機会を・・・・」
まぁ、観たかったらお盆以外に行けと言うことで。


駐車場に到着。真っ白っ!

岬の場所はこの辺。
早速、アゼチの岬へ。

入口。

アゼチの岬:
アゼチの岬はイ琵琶瀬湾(びわせわん)に突き出た岬で、小島・ゴメ島
嶮暮帰島(けんぼっきとう)を望め、遥かに琵琶瀬湾(びわせわん)、
浜中湾の海岸線を見渡すことができ、真夏の落 日は素晴らしいもの
です。海鳥の聖地となる小さな島や岩があり、多くの海鳥が生息し、
浜中町の鳥「エトピリカ」が営巣します。

霧多布岬と同じく、ここにもAR SPOT。

石川五右ェ門登場。

遊歩道を歩いて行くと・・・・

アゼチの岬到着っ!

て、天気が・・・・・
嶮暮帰島、ここから見たかった。
この後、厚岸に行く途中で見たけど。

「どんべえ」に会えなかったけどルパンに
会えたからヨシ。と思いつつ見学完了。
この後、浜中町総合文化センター内にある
モンキー・パンチ・コレクションへ。

到着っ!
な、なんと、お盆で休館。

「ヤツはとんでもないものを盗んでいきました。
北海道ツーリングの機会を・・・・」
まぁ、観たかったらお盆以外に行けと言うことで。











































































































